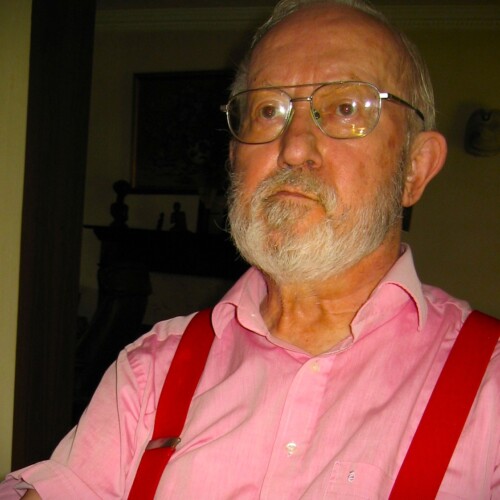一水四見 多角的に世界を見る
小倉孝保

小倉孝保(毎日新聞論説委員)
第2回 死刑廃止の潮流と日本
秋の米大統領選挙は、共和党のドナルド・トランプ前大統領と民主党のカマラ・ハリス副大統領との争いになりそうだ。両者は銃規制や人工妊娠中絶だけでなく、死刑制度を巡っても意見や姿勢を異にしている。
トランプ氏は死刑を維持する立場だ。大統領時代には、任期が切れる直前に次々と執行を命じた。連邦政府は約130年にわたり、政権移行期には死刑を執行しなかった。「慣例」破りの執行命令を疑問視する声も強かった。
一方、ハリス氏はバイデン大統領と同様、死刑に反対の立場である。カリフォルニア州の司法長官時代には、死刑を求刑しない姿勢を示し、犯罪遺族から批判されたこともある。
世界では今、死刑を人権侵害ととらえ、廃止する潮流が加速している。国際人権NGO「アムネスティ・インターナショナル」の報告によると、2023年末時点で死刑を廃止している国は144に上る。法的には制度を維持しながら長年執行していない「事実上廃止国」を含む数字である。
国連加盟国が193カ国であることを考えると、世界の約4分の3は死刑を執行していないことになる。たびたび人権侵害が問題になるロシアやトルコ、イスラエルやベネズエラなども「廃止国」である。
一方、死刑制度をかたくなに維持しているのは、強権・独裁国家とされる中国、北朝鮮、イラン、シリアなどで、民主主義国家では日本と米国の2カ国のみだ。主要7カ国(G7)や経済協力開発機構(OECD、38カ国)でも両国のみが維持している。
米国でも廃止の動きが生まれている。50州のうち23州が廃止し、3州が執行停止中だ。バイデン氏は2021年の大統領就任時、連邦レベルでの執行停止を決めた。現在G7首脳で死刑を支持しているのは日本の首相のみである。
死刑廃止の源流は欧州にある。第二次世界大戦の反省から、人権尊重の流れが強まり、1949年には欧州評議会が設立された。西ドイツはこの年、ナチスによる人権侵害を反省し、死刑を廃止した。
英国やフランスは戦後も死刑を維持し、多数の市民がこの制度を支持していた。しかし、1960年代以降、死刑確定事件で冤罪が判明するケースがあり、廃止機運が高まっていく。英国は69年に廃止し、フランスは81年、議会が廃止を決議した。当時のミッテラン大統領は死刑囚7人を終身刑に減刑し、死刑の歴史に終止符を打った。
欧州で今、制度を維持しているのは、「欧州最後の独裁国家」と呼ばれるベラルーシだけである。欧州連合(EU)は死刑廃止を加盟条件にしている。
日本でも80年代に4人の死刑囚に対する再審で無罪が確定した。それでも政府は死刑をかたくなに維持した。その結果、日本は民主主義諸国では珍しく死刑を維持する国となっている。
しかも、日本については執行方法に対しても、国際人権機関や人権NGOから批判が強い。米国では、絞首刑は残虐な刑罰とされ、薬物注射が使われている。透明性確保の観点から執行時のジャーナリストの立ち会いも認められている。
一方、日本では明治以降、絞首刑を採用し、執行は本人や弁護士にさえ、事前に告知されない。執行後に連絡を受け、初めて命が奪われたと知る。執行が本人に事前に告知されないのは日本とベラルーシだけだという。
ジャーナリストの立ち会いも認めていない。どうやって執行されたのか。最期に死刑囚は何を語ったのか。それを知ることは不可能である。
9月には、死刑囚の袴田巌さんに対する再審で無罪が言い渡される可能性が高い。死刑制度や再審のあり方について、議論を深める絶好の機会になる。
国連総会は繰り返し、死刑を維持する国に執行の一時停止を求めているが、日本は無視し続けている。
世界の流れに気付かず、人権侵害を続けた旧優生保護法の例もある。死刑制度についても国際社会の声に耳を傾けなければ、いつまでたっても日本は「人権後進国」である。
小倉 孝保(毎日新聞論説委員)
小倉孝保(おぐら・たかやす)
1964年生まれ。毎日新聞カイロ、ニューヨーク、ロンドン特派員、外信部長などを経て現職。小学館ノンフィクション大賞などの受賞歴がある





は株価上昇の象徴。-500x500.jpg)
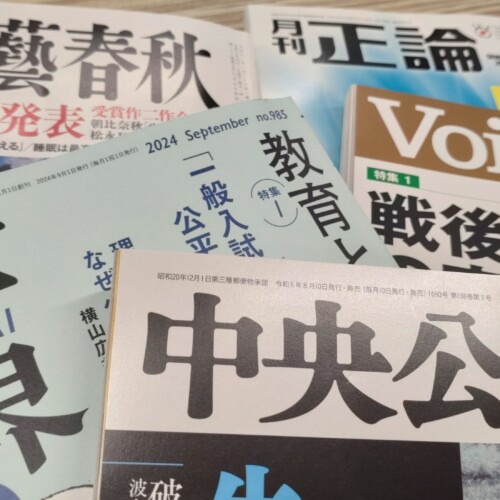

-500x457.jpg)