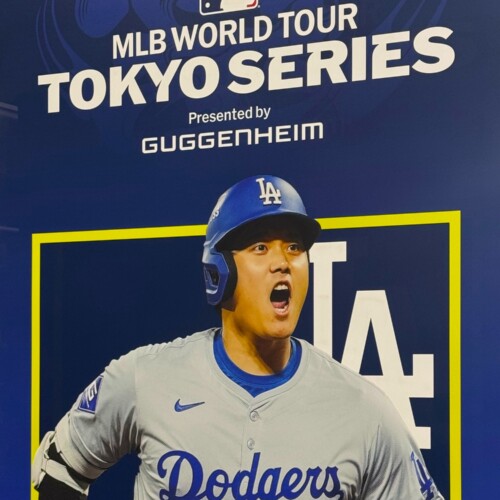牧原出氏インタビュー 古い政治の終わりと改革の課題(全2回)
第2回 政権交代を前提とした政治改革

◇待ったなしは政党と官邸主導の改善
日本政治において問題なのは長期にわたって野党だった党が与党になることを見通せないことでした。今回の政治改革を一つの大きなステップにしなければならないと思います。政治資金問題で終わることはなく、さらなる統治構造改革に向けて与野党で政策競争していただきたいと思います。
私が改革待ったなしと考えるのは、政党と、官邸主導の問題です。政党については先に(第1回で)述べた通り、ガバナンスが重要です。幹部や党中央のガバナンスを担う職員の安定的な雇用環境も含めて、党の政策形成能力を作っていくことが必要です。もう古い自民党とは本当に決別するときに来ているのです。
そして官邸主導、官邸のあり方については合理的に捉え直してバージョンアップしていく必要があります。官邸と官僚の関係、官僚の働き方の問題も重要です。官邸がしっかり政策を主導するのは当然ですが、各省は官邸への忖度ではなく、自発的に政策革新のいい球を投げていく。官邸はその中からいいものを拾っていく。そして各省とのバランスをとっていかないといけません。今はかなり重心が官邸側に寄っている面があるので、線引きしなおす改革が必要です。
私は最近の日本の統治構造の改革を3期に分けて考えています。その第1次が1990年代の政治改革(選挙制度、政党助成など)、規制緩和、省庁再編、地方制度改革です。次が今世紀、福田政権当時からの一連の流れが第2次と位置づけられます。消費者庁、公文書管理、デジタル庁、そして第2次安倍政権に入ってからの安保法制、公務員制度(内閣人事局設置)と続くものです。第1次がパソコンで言えばOS(基本ソフト)、2次が個別のアプリにといった感じでしょうか。そして今から始まるのが第3次ですが、今回の政治資金問題がその始まりになるでしょう。第1次では政権交代を将来の課題とは捉えていましたが、そのための制度上の手当をする訳ではありませんでした。今度は政権交代を本格的に受け止め、それを前提とした政治改革が必要になってくると思います。
◇公務員制度と戦略家の育成
公務員制度は、官邸と各省の関係も大きいですが、ひところの公務員バッシングが一段落した現在の問題としては、公務員の優遇、せめて民間大企業並みの待遇にすることが必要です。公務員だから勤務環境が劣悪でいい、というのでは人材は集まりません。
どうしたら公務部門に優秀な人材を集め、繋ぎ止めることができるか。米英では90年代から議論されていましたが、日本でも問われるようになりました。海外では公務員の年金保障が格段に厚い国もありますが、日本社会では官僚へのそうした待遇が許されるのかという難しいところもあります。
さらに大事なのは、本当の意味での戦略家を日本の公務員制度の中で作れるかということです。90年代には民間から人を入れればできると思っていたのです。しかし、実は日本は中央・地方関係の比重が大きく、民間の人にはイメージできない公務員が形作る世界があります。地方と国の公務員の世界に民間の人が入っても、「行政の何を知っているんですか」と言われてしまいます。経済と国際関係は民間の知恵でできるところがありますが、中央・地方関係は難しい。内政が結構重いのです。ですから、内政分野の公務員をしっかりと育てないと、内政の戦略が出てこないと思います。
◇国と地方の関係の再構築へ「内政諮問会議」を
これは国と地方の関係につながってきます。コロナ禍でもそうでしたが、高齢化が進み地方自治体の足腰が弱ってきているので、自治の受け皿になれない町村が出てきてしまいます。分権の流れという議論はその通りかもしれませんが、強い自治と弱い自治が出て来るのです。そういう格差を前提に分権などの制度設計を考えていく必要があります。
その場合、国の側で自治体をしっかりモニターする仕組みがないといけません。人間ドックで自治の健康診断をするような仕組みです。こうした機能が、富裕な強い自治体と貧乏な弱い自治体の格差が広がってくる中で重要になってきます。そうしないと、富裕な自治体が貧しい自治体について「国の指示待ちだからダメだ」などと批判するような、金持ちの優等生が貧乏な劣等生をいじめるような事態が起きてしまう。財政力の弱い自治体をどうするかという問題を、国だけではなくて、富裕な自治体も一緒に考えていかないといけないのです。
旧自治省は今回もコロナで非常に重要な役割を果たしました。自治体と国とのコミュニケーションは結局自治官僚でないとできない所があります。副知事とか副市長、自治体の総務や財政の部長とかを出していて、首長も多く出している。結局、総務省を中枢の機関で置くしかないと思います。現在の1府12省体制を、1府・総務省・11省のような形で考えるような姿です。
外交と経済では、国家安全保障局や経済財政諮問会議などがありますが、内政のこの部分は各省縦割りで放置されています。国と自治体の関係が密接になる枠組み、それを行う国の組織が必要になると思います。感染症も国と自治体の関係が悪いから齟齬が生じたわけです。1800もの自治体で一度に問題が起こったらさすがに国も対応できませんから。一方では東京などグローバル競争で戦わなければならないところもあります。まさに多様性の表れですが、それらを全体としてどういう絵柄を描いていくのか。例えば「内政諮問会議」というようなものを立ち上げ、各省出身者からなる事務局があって、社会保障、インフラ、街作りなど、いろいろな分野の専門家が横断的に国のあり方を議論する。さらに学会もこうした文や横断的な議論をするような、そういう仕組みがあるといいと思います。
道州制という議論がありますが、制度化を終えるまでのプロセスがあまりにも長すぎます。例えば関西広域連合が動いている関西だけを、州に格上げする考え方もあります。全国一斉に走らせるのは難しいと思います。私は国の行政機関の地方移転懇談会のメンバーでしたが、文化庁と統計局と消費者庁は部分的に関西に移りました。しかし関西にしか移らないのです。東は東京が中心で、西は京都大阪神戸のエリアです。歴史的に価値のある都市の集まりなので、それを生かすのがいいと思います。
いろんなものを平準的に考えた制度が戦後ずっと続いてきましたが、その後の社会状況の変化で勾配が生じています。その勾配をつかみ取った仕組みでやった方がいいと思うのです。平準化に戻すのはもはや無理です。
◇そのほかの改革課題
選挙制度については、いろいろ議論がありますが、理想の制度というのはないので、今の制度を変えるのはできるだけやらないほうがいいと考えます。(参院選挙区の)合区をどうするかというのが当面の課題ですね。人口割でいいかと言う議論もあります。これは国会改革とも関連してきます。
国会改革の中では、政治資金監査の第三者機関ではないですが、国会と政党が独自の調査をする必要が出てくる中で、特に安全保障とか機密情報の問題が膨らんでくると思います。アメリカ連邦議会のように政府の機密情報を扱う秘密会ができるのかが問われてくるでしょう。
◇日本にポピュリズムは育ちにくいが
日本は欧米のようなポピュリズムは中々優勢にはならないと思います。日本は地方に真面目な人が多く地方に行けば行くほど、お互いが膝詰めのような世界です。悪く言えば息苦しいほどです。一方、都市部でそれほど格差が広がっているかというと、それほどでもないのです。外国人も比較的少ないので排外運動も広がりにくい。結局、右派政党が伸びていく感じにはならないようです。右派の元と言われる陰謀論が出てきても、むしろシニカルに見て共有するリテラシーがあるようです。
もし日本にポピュリズムが起こるとすると、海外で反日運動が起きたときに、その反作用として起こることがありうると思います。かつて拡大した嫌中、嫌韓のような形です。また、昨今の裏金問題を引きずる政治のもとでは、日本型のポピュリズムとして、政治家バッシングが連鎖するということがありうると思います。これは第1回でも述べたように、公費を使う政治家への国民の目が厳しくなっているという背景事情にもとづいています。一つネタが見つかると集中してバッシングが起き、同調圧力からくる村八分的なポピュリズムが拡大することが考えられます。このような事態を避けるためにも、政治資金の透明化と第三者機関による監視などによって政治の信頼を回復することが重要だと思います。
(取材・構成 冠木雅夫)
牧原 出(まきはら・いづる)
東京大学先端科学技術研究センター教授(行政学、日本政治史)。
1967年生まれ。東京大学法学部卒。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス客員研究員、東北大学大学院教授を経て2013年より現職。著書に『 内閣政治と「大蔵省支配」』(中央公論新社)、『崩れる政治を立て直す』(講談社)、『田中耕太郎』(中央公論新社)など。






-1-500x428.jpg)