『検証 フジテレビ問題』を検証する
臺 宏士(『放送レポート』編集委員)

フジテレビHPより
検証番組の内容・証言──
「公正性」と「透明性」担保できず
元タレントの中居正広氏とフジテレビ・元アナウンサーの女性との間で起きた「性暴力」問題をめぐり、フジテレビは7月6日、『検証 フジテレビ問題~反省と再生・改革~』〔註釈〕と題する番組を放送した。「フジテレビの対応の誤り」と「組織の構造的な問題」を検証したという。しかし、日枝久・元取締役相談役や中居氏、問題の発端となった会食への参加を女性に呼び掛けた元編成部長ら重要人物が出演しないなど物足りなさは否めない。検証番組には何が欠けていたのか──。

「中居問題」を巡るフジテレビの会見などを詳報するスポーツ紙と全国紙=中澤雄大撮影
◇「日枝氏には取材できず」
番組は検証項目の一つとして日枝氏の「権力と責任」に焦点を当てた。1988(昭和63)年に50歳で社長に就任。2025(令和7)年3月に退任するまで約40年にわたって君臨し、人事権を握り続けた。番組は人物像を「企業風土を形成するうえで大きな影響を与えた」と評した。公の場で釈明しないまま退かせるのか、検証番組の力量が試される点だ。
「日枝氏とその他の役員とでは大きな権力格差が存在した。多かれ少なかれ忖度はあった」(豊田皓元社長)。「日枝さんに歓心を得ようとしている役員、局長の動きが若い人間のモチベーションを極端に下げた」(遠藤龍之介元副会長)。元側近が弊害を明かす一方で、尾上規喜・元監査役は「日枝に責任をかぶせるのは簡単。取締役(会)として経営責任を全体で担う」とかばい、「“諸悪の元凶が日枝だ”っていう世論の動きには納得できない感じではありました」と心情を代弁した。しかし、最後まで日枝氏自身の出演はなかった。
の体制長期化の影響を明かした豊田皓元社長の書面の一部(『検証-フジテレビ問題』より)-300x168.jpg)
日枝氏(中央)の体制長期化の影響を明かした豊田皓元社長の書面の一部(『検証 フジテレビ問題』より)
-300x171.png)
フジテレビ問題「検証プロジェクト」チームが日枝氏に出した取材依頼文書(『検証・フジテレビ問題』より)
「私たちは日枝氏に3回にわたり取材を申し込みましたが、日枝氏は応じませんでした」。ナレーションとともに「フジテレビ問題『検証プロジェクト』チーム」名で日枝氏に宛てた「フジテレビ『検証番組』取材のお願い」の依頼文が画面に大写しとなった。日付は4月1日。第三者委員会(委員長・竹内朗弁護士)が調査報告書を公表した翌日だ。なしのつぶてだったのか、断りの返事が届いたのか、日枝氏の対応は触れられていない。
の経営者像を語る遠藤龍之介元副会長(『検証・フジテレビ問題』より)-300x167.jpg)
遠藤龍之介元副会長(奥)は1月27日のフルオープン記者会見の前日、日枝氏に辞任を迫り、拒否されたことを明かした(『検証・フジテレビ問題』より)
の記者会見(25年3月31日、東京・台場のフジテレビ本社で)臺宏士撮影-300x134.jpg)
調査報告書を公表した第三者委員会(竹内朗委員長)の記者会見(25年3月31日、東京・台場のフジテレビ本社で)=臺宏士氏撮影
フジ再生のカギは検証番組の内容にかかっていると、筆者は考えていた。役員数を半減し、女性取締役を3割に増やす新体制を打ち出し、再生・改革プランをぶち上げたとしても、失墜した報道機関への信頼は自らが検証できていなければ回復にはつながらない。その一つは、日枝氏に視聴者に対して今回の事態について番組を通して語らせることだった。
フジは4月30日に公表した「再生・改革に向けた8つの具体策」の一つとして「『楽しくなければテレビじゃない』から脱却し、放送法の原点に立ち返り、公共性をもって社会から必要と認められる企業となります」と宣言した。「楽しく……」は1980年代に数々の人気番組を生み出し黄金期を築いた「日枝路線」のキャッチフレーズであり、それとの決別で、さらに日枝氏のインタビューの重要性は増した。
臺宏士撮影-300x179.jpg)
夕刻から未明まで約10時間半に及んだフルオープンの記者会見(25年1月27日、フジテレビ本社で)=臺宏士氏撮影
筆者は1月27日の記者クラブメンバー以外にも開かれた記者会見、3月31日の第三者委員会の調査報告書の公表後に開かれたフジの記者会見、そして5月25日の株主総会後の囲み取材――の3つの節目で、検証番組において日枝氏を含む関係者へのインタビューの実現性について経営陣の見解を繰り返し尋ねた。
臺宏士撮影-225x300.jpg)
株主総会後に質問に応じる清水賢治フジテレビ社長(25年6月25日、フジテレビ本社で)=臺宏士氏撮影
遠藤氏は「23年6月から知っているメンバーが取材を受けるのは当然」(1月)と日枝氏については明言せず、清水賢治社長も「ご本人が判断することだと思う」(3月)、「検証番組の内容については、私は一切タッチしていない」(6月)と距離を置いた。清水氏は番組内で「日枝氏は何らかのコメントを出すべきじゃないか」と述べていたが、そのためにどのような努力をしたのかは明かさなかった。
世の中の目から逃れようとする「疑惑」の人物を捕まえてこそ、報道機関による取材ではないのか。自宅等で待ち構え対象者にマイクを突き付けるのは、テレビメディアの最も得意としてきた手法のはずだ。こうしたどこまでも追いかけようとする映像はなかった。日枝氏のコメントは結果として得られないにしても、あらゆる手段を尽くして日枝氏に語らせようとするフジ再生に直結する制作者の気迫と熱意が伝わってこなかった。視聴者らが何よりも注目したであろう最大のポイントが肩透かしに終わったのである。
◇編成部長や中居氏も取材拒否? 可能な限りの透明性の欠如
元編成部長や中居氏も日枝氏と同様に検証番組には出演していない。調査報告書によると、「事件」の2日前、元部長は中居氏の求めに応じて急きょ同氏所有のマンションで開くことになった会食に「仕事でプラスになる」などとして女性に参加するよう声を掛けた。第三者委員会はこれを「業務」と認定し、「性暴力はフジの『業務の延長線上』で発生した」と判断した根拠の一つとなっている。
元部長は「事件」後も中居氏から相談にのり、同氏から託された100万円を入院中の女性に届けたり、自社番組に出演する弁護士を紹介したりするなど一貫して中居氏側にいた。フジが6月に「二次加害となり得る不適切な行為」として4段階の降職処分にした人物だ。
二人の深い繋がりはどのように生まれたのか。元部長と中居氏の関係をよく知る社員の証言を通して浮かび上がったのは、テレビ局に存在する明確な上下関係だった。
「中居氏からの突然の電話があって、外せない業務を除いてはプライベートも投げうって一目散に飛んでいく」。ある社員の元部長評だ。「タレントと局員、制作者は初めて出会ったときの(上下の)関係性がずっと保たれていくのが慣例」と明かす。

黄昏時のお台場。左手にはフジテレビ本社ビル
別の社員はバラエティー部門で出世した背景について「特定の力の強いタレントと距離が近く、大型特番を作りヒットさせていることが社員として評価される実情はあった」と証言した。元部長が中枢である「編成部長」に抜擢されたのは中居氏の新番組『まつもtoなかい』(23年4月)の立ち上げの2カ月後で、「事件」が起きた時期と重なっていた。
しかし、日枝氏と同様、周囲の関係者による証言だけで、中居氏と元部長はなぜ出演していないのか。日枝氏と異なるのは、取材を申し込んだのかどうかさえ明らかにされていなかった点だ。検証の信頼性を担保するのはその過程に対する可能な限りの透明性だ。その視点は総じて弱かった。
◇中居氏側の反論など──検証からこぼれ落ちた多くの論点
中居氏は5月以降、第三者員会を相手に調査報告書に対する反論を始めた。報道によれば、「『性暴力』という日本語から一般的に想起される、暴力的または強制的な性的行為の実態は確認されなかった」などとする見解を示し、資料の開示を求めた。
7月5日にも「救済手続も、名誉回復の手段もなくまさに『言いっぱなし』」などと批判したという。1月9日に中居氏が発表したコメントには、「一部報道にあるような手を挙げる等の暴力は一切ございません」との記載がある。
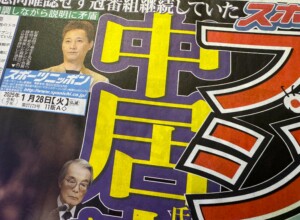
中居・フジテレビ問題を追及するスポーツ紙(写真は『スポーツニッポン』)=中澤雄大撮影
「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」とする放送法4条を持ち出すまでもなく、反論は番組として中居氏側に取材して、中居氏の言い分に理がなければその根拠を示して批判すべき要素の一つであり、現時点で視聴者や関係者が最も知りたかった点ではなかったのか。
いまなお自らの口で語らない中居氏だが、取材を申し入れても応じてもらえなければ、そう報じればいいのではないか。
さらに、第三者委員会が調査報告書を出した3月31日以降に起きた出来事は、今回の検証対象にはほとんどなっていなかった。3月以降に矢継ぎ早に出された改革・再生プランの実効性はあるのか。6月5日にはフジテレビは港浩一元社長と大多亮元専務(関西テレビ前社長)に対して法的責任を追及する訴訟の準備に入ったことを発表している。旧経営陣への責任追及は2人にとどまってよいものなのか。
6月25日に開催されたフジ・メディア・ホールディングス(HD)株主総会で、中居氏への損害賠償の有無を尋ねられた清水氏は「検討している」と答えた。同じ日の囲み取材でも「弁護士に見解を求めている。その中で(訴訟の有無は)検討していく」と述べている。
こうした会社の方針に対して、番組はどうとらえているのか。検証対象にはなっていなかった。加えて、番組で欠けていたのは大事な検証項目だけではない。検証組織の説明もなかった。
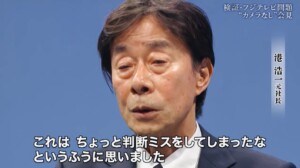
一連の問題を振り返る港浩一元社長(『検証・フジテレビ問題』より)
-300x166.jpg)
問題の経過などを振り返る大多亮元専務(『検証・フジテレビ問題』より)
番組を制作したのは、「フジテレビ問題検証プロジェクトチーム」とされるが、それだけだ。今回のように自社が抱えた問題を関係者が調査をする場合、重要な点の一つは検証結果の公正性を担保するための組織の独立性だ。どういうメンバーで組織され、最終的な責任者は誰なのか。独立性を確保するため、どのような工夫を重ねたのかは、番組として説明責任を果たすための重要な要素だが、番組内では触れられなかっただけでなく、ホームページでの記載もない。
検証工程の全体像の説明がなかったため、「チーム」が示した判断の公正性は評価しようがない。清水社長が「報道の独立性を重んじている。内容に口を出していない」と記者に説明しただけでは全く足りない。
=臺宏士撮影-300x212.jpg)
フジHDの株主総会の受付前には100人以上の株主が並んだ(25年6月25日、江東区の有明アリーナで)=臺宏士氏撮影
◇疑問符を付けざるを得ない検証内容
さまざまな論点が検証対象からこぼれてしまったのは、第三者委員会が調査報告書で示した枠組みと事実関係に、かなりの部分で頼ったことが要因ではないだろうか。検証の出発点である対象範囲や、検証できること・できたこと、できないこと・できなかったことが明示されていないため、問題の全体像、立体的な構造がはっきりと伝わってこなかった。
フジへの信頼が失われている中での検証は、番組制作過程の透明性の確保と枠組みをはっきり明示しなければ視聴者に信用されない。この種の番組は「身内による検証だから何か隠しているに違いない」と、そもそも疑われているのだ。「取材の詳細は控える」といった従来型の広報対応などはもってのほかだ。
例えば、調査報告書がその存在を指摘したタレント等の取引先と行われていた「性別・年齢・容姿などに着目して呼ばれる会合」で、大多氏が女性アナウンサーを「上質なキャバ嬢」と評したのは衝撃的なエピソードだった。大多氏と港氏の事例が取り上げられたが、2人だけにとどまるのか。確認できたのはどの範囲の幹部で、過去はどこまで遡れたかどうかの説明はなかった。あるいは2人しか取材しなかった、もしくはできなかったのか、疑問の余地がある。
臺宏士撮影-214x300.jpg)
フジテレビ本社(東京都港区台場)=臺宏士氏撮影
このため検証番組は、全体として既視感を払拭できなかった。会社は元部長ら5人の処分に当たって「調査報告書に記載された内容を踏まえつつ、改めて外部の弁護士において、相当な時間を掛けて、被害に遭われた方をはじめとする関係者への事実確認や救済に関する意向確認等を実施しました」と明かしている。それでは検証番組ではどう報告書を位置付けたのか。その説明もなかった。
2人のコメンテーターは番組が準備したVTRに沿って見解を述べるという役割だった。これでは検証に欠けていた論点についての議論はしようがなく、筆者が指摘したような一連の疑問点は両名からは示されなかった。厳しく言えば、「第三者委員会にご指摘を受けた点はこうでした」式の狭い枠組みの検証で自立した再生が期待できるのか。疑問符を付けざるを得ない(ただし、会合メンバーに指名され参加しながらも疑問を抱き続けた女性アナウンサーの証言や、被害女性の訴えを受け止めきれず、後悔を語る当時の報道局編集長の実名・顔出しでのインタビューなど生の声からは、「セクハラを中心とするハラスメントに寛容な企業体質」「全社的にハラスメント被害が蔓延」と第三者委員会から指摘を受けた実態をさらけ出し、再生しようとする関係者の気持ちがよく伝わった)。
再度の検証を強く求めたい。
〔註釈〕
『検証 フジテレビ問題~反省と再生・改革~』の概要
2025年7月6日(日)午前10時から1時間45分にわたってCMなしで放送された。冒頭、清水賢治社長が中居正広氏から「性暴力」被害を受けた元アナウンサーの女性に対して「人権を救済するために必要な対応ができなかった。大変申し訳なかった」などと謝罪。▽第三者委員会の調査報告書の認定に沿って、関係者が女性の訴えを受け止められなかったことへの反省▽1月17日に開いた記者会見(放送記者会主催)が、記者クラブの加盟社など一部に参加を限定した上、テレビカメラの撮影を禁止した理由に関して、港浩一元社長らの関係者による釈明▽第三者委員会から「今回の人権侵害を助長した」と指摘された芸能事務所やタレントらの歓心を得るための「性別・年齢・容姿に着目した会合」に関する、港氏や大多亮元専務らによる証言▽ハラスメント被害の申告に対する不適切な対応▽日枝久・元取締役相談役による「長期支配」の弊害▽新入社員を含む現場社員による再生に向けた決意表明――などのパートで構成された。
番組側が準備したVTRに対して、ノンフィクションライター(元毎日新聞記者)の石戸諭氏と企業経営に詳しい矢守亜夕美氏がコメントしたり、同席する清水社長に質問したりする形で進行した。検証番組は現在、YouTubeフジテレビ公式チャンネルと、TVer(7月13日23:59終了予定)から視聴できる。

臺 宏士(だい・ひろし) メディア総合研究所『放送レポート』編集委員、跡見学園女子大学兼任講師
1966年、埼玉県生まれ。早稲田大学卒。毎日新聞記者時代から、放送などメディア問題の調査研究に取り組む。現在、特定非営利活動法人「報道実務家フォーラム」副理事長、早稲田大学総合研究機構招聘研究員、新聞労連ジャーナリズム大賞選考委員。主な著書に『報道圧力──官邸VS望月衣塑子』『アベノメディアに抗う』、共著に『僕らはまだテレビをあきらめない』『「表現の不自由展」で何があったのか』『エロスと「わいせつ」のあいだ──表現と規制の戦後攻防史』など多数。
と弾劾反対派(右)の横断幕が掛かっていた。韓国社会は分断が一層深まっている=2025年3月11日-800x550.jpg)





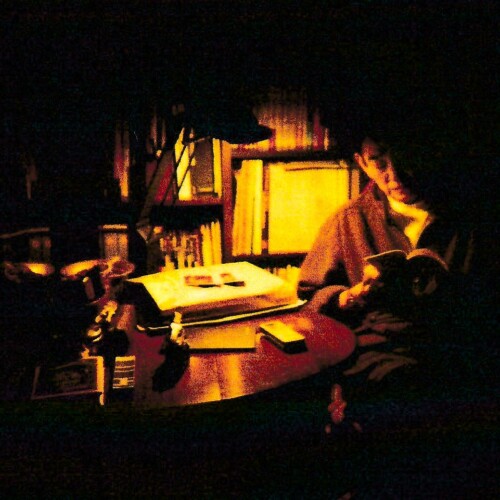



-500x388.jpg)