戦後80年 歴史認識の変革を
佐藤 卓己(上智大学教授)
.jpg)
1945年9月2日、米戦艦ミズーリ号の甲板上で降伏文書に署名する重光葵・日本政府全権、右は随員の加瀬俊一・外相秘書官。見守るのはサザーランド米陸軍中将(米陸軍撮影)
8月ジャーナリズムと「歴史のメディア化」
戦後80年は、あの戦争を実体験した世代自身が何かを語り残すことができる最後の周年ジャーナリズムである。逆に言えば、十年後の戦後90年、2035年における百歳の語り部たちはすべて元「少国民」となる。原爆などの戦災体験はともかく、戦闘経験をもつ語り部はいない時代となる。戦争報道が戦災に偏することは、これまでの8月ジャーナリズムでも指摘されてきた。8月ジャーナリズムとは、8月6日(ヒロシマ原爆忌)から8月15日(終戦記念日)の間に戦争報道を集中させる日本特有のメディア現象である。今後はますます戦災、つまり被害の語りがその中心になっていくはずだ。
◇重視されるのは内容の真偽よりも宣伝効果
歴史認識において、加害責任を追及されることは忌避されるため、だれもが被害者のポジショナリティ(立ち位置)を追い求める。そのため「歴史のメディア化」は加速する。メディア化とは、すなわち広告媒体化である。周知のごとく、メディア mediaはラテン語 medium(中間・媒介)の複数形である。英語では中世から「巫女・霊媒」など主に宗教的な意味で使われてきたが、今日的な「メディア」の初出例として『オックスフォード英語辞典』は、1923 年アメリカの広告業界誌『広告と販売』に登場した、新聞・雑誌・ラジオの広告三媒体を指すmass mediumを挙げている。日本でも1970年代まで「メディア」は広告関連の業界用語だった。メディアが広告媒体である以上、そこで重視されるのは内容の真偽よりも宣伝の効果である。
実際、歴史は今日ますますプロパガンダ、つまり政治広告の道具となっている。直近の事例では、ウクライナ侵攻の中で実施されたロシアの対独戦勝記念日(5月9日)における歴史の政治利用がある。これまでもプーチン大統領は戦争目的を「ウクライナの非ナチ化」とし、「対ファシズム戦争」への協力参加を中国や北朝鮮に呼びかけてきた。当然、日本国民としては、今年の「九三抗戦勝利記念日」で中国がどのようなプロパガンダを展開するかに注目すべきである。しかし、日本のメディアが8月ジャーナリズムに固執する以上、9月に適切な国際報道を期待することはむずかしいのではないか。
◇8月15日の記憶、9月2日の歴史
20年前の戦後60年に際して、私は『八月十五日の神話―終戦記念日のメディア学』(ちくま新書・2005年)を公刊した。8月ジャーナリズムは戦争記憶の継承よりもその忘却とメディア化、つまり政治利用に向けて補助線を引くイベントになっているのではないか、との問題提起である。同書は戦後70年を前に増補版(ちくま学芸文庫・2014年)となり、戦後80年のいま、ハングル版、トルコ語版につづき英語版の作業が進行している。それにしても、正直言えば、私は20年間も同じ議論を繰り返すことになろうとは思っていなかった。
 -300x222.jpg)
昭和20年8月14日付の「終戦の詔書」原本の一部 (国立公文書館所蔵)
事実関係と客観性を重視する歴史家の視点で見れば、日本の終戦日はポツダム宣言を受諾した8月14日、あるいは降伏文書に調印した9月2日である。敗戦直後に日本政府が認定した終戦日は前者であり、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)占領下の新聞が報じた降伏記念日は後者である。現行の8月15日は国民感情への働きかけを最大化すべく、メディアの論理で選ばれた記念日なのである。というのも、満洲事変以後は戦前にも毎年8月15日に戦没英霊供養の盂蘭盆会法要がラジオ中継されていた。その伝統に玉音放送の記憶を重ねた「戦後10年」のメディアイベントによって、8月15日は終戦記念日と認識されることになった。その根拠規定は、戦後18年が経過した1963(昭和38)年5月14日に第二次池田勇人内閣で閣議決定された「全国戦没者追悼式の実施に関する件」であり、現行の「戦没者を追悼し平和を祈念する日」は1982(昭和57)年4月13日に鈴木善幸内閣で閣議決定されている。この「新しい伝統」は、新聞、雑誌、ラジオ、テレビで繰り返された8月ジャーナリズムが創った集合的記憶なのである。
-300x197.jpg)
8月15日に開催されている全国戦没者追悼式(厚生労働省ホームページより)
確かに1945(昭和20)年8月15日正午からラジオで流された玉音放送は、国民的記憶として刷り込まれている。だが当時、すべての日本人がその放送を聴取できたわけではない。沖縄では放送局が破壊されており、短波受信機を持たない民間人で聴いた人はほとんどいない。また同時刻も鉄道は動いており、移動中の乗客はむろん聞いていない。それ以上に問うべきは、体験記憶の真実性である。
北海道で書かれた玉音放送の回想にも「ジリジリ照りつける太陽の下で」、「真っ赤な太陽は真上にあった」などの表現が登場する。しかし、山本竜也「1945年8月15日の北海道の天気」(『北海道の文化』第91号)によれば、その日の正午、道内はおおむね曇り、一部で雨が降っていた。気温は太平洋側でもほぼ20度未満、夏日の地点は一カ所も確認できない。山本氏は天気や寒暖について記載のある道内83人分の8月15日の回想を分析している。肌寒い冷夏だったにもかかわらず、道民の多くがこの日を「晴れて暑い日」だったと回想している。一方で、当時の日記13編には「曇り」や「雨」の記載があることも確認されている。つまり、後年の回想は現実の体験ではなく、戦後に映画やテレビで構築された集合的記憶なのである。
◇終戦よりも開戦が重要
こうしたメディアイベントによる終戦の集合的記憶は、はたしてグローバル時代に生きる日本人の歴史理解にふさわしいものだろうか。国際的視野で戦争責任を論じるためには、終戦日よりも開戦日、つまり12月8日(1941〔昭和16〕年・真珠湾攻撃)なり、満洲事変の9月18日(1931〔昭和6〕年・柳条湖事件)を記憶するのが適当だろう。「なぜ戦争を始めたのか」という開戦責任の問いはありえるが、「なぜ戦争をやめたのか」と責任を問う議論が敗戦国で可能であろうか。戦争の敗者には、多くの場合、選択の余地が残されていないためである。むろん、「なぜ終戦が遅れたのか」を問う責任論はありえる。しかし、「玉音放送による終戦」という枠組みでは、昭和天皇の「御聖断」、つまり英断に焦点が当たるのが自然である。
それでも敢えて終戦日に注目したいなら、それはグローバル・スタンダードである欧米の9月2日(VJ Day〔Victory over Japan Day〕/対日戦勝記念日)にあわせるべきだろう。戦争とは相手のある外交事項であり、他者の存在は無視できないからである。しかし、8月15日を終着点とする8月ジャーナリズムは、外国を無視して歴史的事実より国内の共感を重視する「歴史のメディア化」の実践となっている。
また、外交関係者からは北方領土問題への配慮から、9月2日を終戦日とすることへの反対論が聞こえてくる。ソビエト軍の北方領土侵攻を終戦日以後に始めた「違法行為」と主張する立場である。しかし、8月15日以後に本格化した「日ソ戦争」の記憶を抑圧し、北方領土問題から国民的関心を遠ざけてきたのも、また8月ジャーナリズムではなかっただろうか。
◇新しい理知的な「9月ジャーナリズム」を
私は増補版(ちくま学芸文庫)で、9月ジャーナリズムを提唱する文章を新たに補論とした。もっとも、戦後60年の原著でも「戦没者を追悼し平和を祈念する日」を二分割して、8月15日の「戦没者を追悼する日」と別に9月2日に「平和を祈念する日」を新設する、現行記念日の政教分離を主張していた。私たち人間は祈りながら同時に討議できるほど器用な生き物ではない。追悼する日と議論する日を切り分けてはじめて、宗教的心情にも政治的議論にも正面から向き合うことができるはずなのである。8月の個人的な記憶が大切であればこそ、それを政治的議論と安易に重ねるべきではない。8月の国民感情を十分に踏まえてこそ、9月に周辺諸国との理性的な討議が可能なのではないだろうか。
-1-199x300.jpg)
増補版『八月十五日の神話』(ちくま学芸文庫)
その上での9月ジャーナリズムは、夏休み明けの教室にふさわしい歴史教育であるべきだ。1939年9月1日にドイツ軍がポーランドに侵攻することで第二次世界大戦は勃発した。ちょうど6年後の1945年9月2日、東京湾上の戦艦ミズーリ号で日本政府は降伏文書に署名している。同盟国ナチ・ドイツとともに「あの戦争」を戦ったという意識は今日の日本人に乏しい。だが、歴史理解のグローバル・スタンダードでは、第二次世界大戦はファシズムVS民主主義の戦争である。現在もなお日独に対する敵国条項を憲章に含む国際連合(United Nations、中国語表記では「联合国/聯合國」)の世界観を踏まえるなら、「あの戦争」は大東亜戦争やアジア・太平洋戦争という狭い枠組みではなく、やはり第二次世界大戦というグローバル・ヒストリーで理解されるべきだろう。
とはいえ、「あの戦争」が降伏文書の調印で終結したかどうかは別に検討すべき課題である。欧米の大学で使用される日本史テキストでは、1951年締結のサンフランシスコ講和条約発効後を「戦後」とするものが多い。占領期を「戦後」と理解する歴史認識にも8月ジャーナリズムの忘却機能が作用している。何が戦争であり、何が平和なのかを真剣に考えるためにも、第二次世界大戦勃発の9月1日を起点として、サンフランシスコ講和条約調印の9月8日までの期間、新聞でもテレビでも教室でも、戦争と平和について議論することが望ましい。
9月ジャーナリズムでは、9月1日に1923(大正12)年の関東大震災と朝鮮人虐殺を重ねてもよいし、21世紀的な問題関心から9月11日の2001(平成13)年アメリカ同時多発テロを加えてもよい。対中関係を意識するなら1931年満洲事変勃発の9月18日まで期間を延長してもよいのではなかろうか。
いずれにせよ、情緒的な8月ジャーナリズムとは別の、新しい理知的な9月ジャーナリズムが生まれることを私は期待している。ジャーナリズムが歴史で果たす役割とは、未来志向の対話可能なものでなくてはならないはずである。

佐藤 卓己(さとう・たくみ) 上智大学文学部新聞学科教授、京都大学名誉教授(メディア史、メディア文化学)
1960年、広島県生まれ。京都大学文学部西洋史学専攻卒業。ミュンヘン大学留学、京大大学院単位取得退学。東京大学社会情報研究所助手、同志社大学助教授、国際日本文化研究センター助教授、京大大学院教授などを経て現職。著書は『大衆宣伝の神話』(ちくま学芸文庫)、『キング』の時代』(岩波現代文庫=サントリー学芸賞)、『八月十五日の神話』(ちくま学芸文庫)、『言論統制』(中公新書)、『テレビ的教養』(岩波現代文庫)、『輿論と世論』(新潮選書)、『ファシスト的公共性』(岩波書店=毎日出版文化賞)、『流言のメディア史』(岩波新書)、『あいまいさに耐える』(同)など多数。
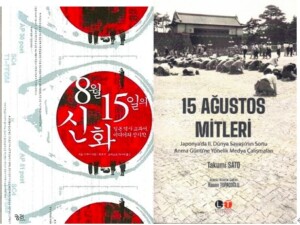
翻訳されたハングル版とトルコ語版『八月十五日の神話』







のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)


