激動の世界に必要な戦略的外交(下)
谷内正太郎・初代国家安全保障局長に聞く

世界と日本外交について大いに語る谷内正太郎・初代国家安全保障局長=中澤雄大撮影
日本はメジャー・プレーヤーとしての覚悟を
◇「対米一本足打法」でなく「広角打法」で
──今後の日本の外交・安全保障はどうするべきでしょうか。大きな流れとしては日本の国力が低下、衰退しています。その一方で、全く逆方向の要請、日本がより大きな役割を求められていると言っていいかもしれません。
谷内 一つ背景としてあるのは、やはり安倍外交です。戦略的外交を長期間やってきたので、国際社会における安倍晋三首相の存在感は大きくなっていました。特に(1期目の)トランプ米大統領との関係が非常に良かった。今、日本の国力は相対的に低下していますが、GDPが世界第4位の大国であることは間違いない。その安倍路線を菅義偉さん、岸田文雄さんが継承していったので、日本の存在感は今でも結構高いものがあると思います。
2-300x220.jpg)
2025年6月に開催されたG7サミットでの記念撮影(ホワイトハウスHPより)
今はトランプ大統領が、アメリカ第一、ディール重視ということで、米国がグローバルリーダー、自由陣営のトップリーダーの地位から滑り落ちつつあることは客観的に言えると思います。個人的には見たくないことですが。
欧米関係も悪くなっていますし、ヨーロッパのNATO(北大西洋条約機構)諸国、EU(欧州連合)諸国、あるいはインド、オーストラリア、ニュージーランド、ASEAN(東南アジア諸国連合)といった国々、つまり自由や民主主義を重視する国々は「これからどうすればいいんだ」という思いを非常に強く持っているわけです。そういう中ですので、日本は自由や人権や法の支配などの価値観を大切にする国々との連携、パートナーシップを強めるとともに、その過程においてリーダー的な役割を果たさなければなりません。日本がトップリーダーになる必要はないのですが、リードする国の一つになることは非常に大事です。

QUADのイメージ図
EUとTPP(環太平洋パートナーシップ協定)諸国を連携させるという議論もあります。合体するのは難しいかもしれませんが、深い連携関係を作るとか。それからFOIP(自由で開かれたインド太平洋)やQuad(日米豪印戦略対話)という日本が提唱したものがあって、これは今のトランプ大統領も否定はしないでしょう。それらをさらに深めていくべきではないかと思います。
象徴的な言い方ですけれども、「対米一本足打法」ではなく、「広角打法」で行くべきだと思います。ある意味では日本の出番なので、特にアメリカのアジアにおけるコミットメントとプレゼンスをしっかり引きつけておくように努力すべきだと思います。
◇今に生きる安倍政権時の構想
――FOIPは、まさに日本発の発想をアメリカも取り入れたものです。安倍政権の外交戦略が今も生きているということですか。
谷内 はい、そう思います。FOIPは2016年にナイロビ(アフリカ開発会議での安倍首相演説)で急に出てきたわけではありません。源流は麻生太郎さんが外相の時に打ち出した「自由と繁栄の弧」という考え方です(06年11月30日、日本国際問題研究所セミナーでの講演)。当時、私は外務事務次官だったのですが、実は、最初に「自由と繁栄の弧」を打ち出した時は、外務省内にも結構反対する人がいました。要するに日本は国際社会にあまり出しゃばるべきではない。それと、かつての英米撃滅、あるいは大東亜共栄圏のようなスローガン外交は駄目だという考えが省内の雰囲気としてありました。
「自由と繁栄の弧」で想定した地域というのは、当時、国際テロがはびこっていて、アメリカが「不安定の弧」と言っていた地域です。いわゆるリムランド(ユーラシア大陸の沿岸地帯、地政学用語)の地域を「不安定の弧」と言ったわけです。しかし、「不安定」というのはネーミングが良くない。そういう地域の国民、人々も「自由と繁栄」を求めて一生懸命努力していることは間違いないので、日本は彼らの伴走者としてともに努力することを目指して「自由と繁栄の弧」と名付けたわけです。
.jpg)
日本記者クラブで講演する麻生太郎外相(2006年1月、外務省HPより)
中心はもちろん「自由」ですが、法の支配、それから経済的なつながりを深める、それらを念頭において考えを出しました。ただ、中国としては、自分たちを大きく包囲しようとしていると見ていたとは思うのですが、想定されるほど激しい批判はなかったですね。
当時は、麻生外務大臣にメジャーな外交演説を1カ月に1回はやっていただきたいという考えがありました。「日本の外務省には外交戦略がない」などと言う評論家の人がいましたし、外交を行っている以上、外交戦略は当然ありますよ、ということも示したかったので、中東政策や対中政策というメジャーな外交の柱についてのスピーチをやってほしいという考えで、その一つがこの「自由と繁栄の弧」だったわけです。
――そのころの麻生外相と安倍首相の関係は?
谷内 そこはちょっとデリケートでしたね。安倍さんとしては、このような大きな話は首相としての自分がやるんだろうという風に、政治家としては当然考えられると思うんです。ただ、安倍さんは「氷を砕く旅」と言う電撃訪中・訪韓をして大きな成果をあげていたこともあってか、麻生外相のこの構想にネガティブな態度を示されることはありませんでした。ご両者の関係はお互いに敬意を持った極めて緊密な信頼関係にあったと思います。
――「自由と繁栄の弧」は先生の命名ですか?
谷内 私が名付けたわけではないけれども、外務省総合政策局総務課長だった兼原信克君(谷内氏が国家安全保障局長時に同次長。現・笹川平和財団常務理事、麗澤大学特任教授)と二人で考えました。民主主義という言葉を入れようかとも議論しましたが、いや、民主主義という言葉は、そうではない国もあるので「自由と繁栄」であれば間違いないのではないかというので。
――インド太平洋というものを一体化して考える発想はいつ頃からでしょうか?
-300x172.jpg)
日本が提唱する「自由で開かれたインド太平洋」図(外務省HPより)
谷内 これは安倍第一次政権の終わり頃にあったインド訪問で、安倍首相が「二つの海の交わり」というスピーチをした時からです(07年8月)。インド洋と太平洋はつながっていて、今ますます連結性が深まっている。特に中国の海洋進出を考えると、そこを一体として考えて、それに自由とか、法の支配を重視する国々がより協力して安定した地域を築いてゆく必要があり、法の支配が特に大事だ、という考え方です。
◇力の体系、利益の体系、価値の体系
――メジャー・プレーヤーとして日本が役割を果たすということは、国際秩序を受け入れるだけではなく、国際秩序を作ってゆく主体、当事者の立場に立たざるを得ないということですが、トランプ大統領のアメリカとの関係をどう考えたらいいでしょうか?
谷内 ここで、そもそも論をしたいと思います。先ほど(<上>で)名前を上げた高坂正堯先生が、彼の本(『国際政治─恐怖と希望』中公新書1966年刊)の中で、各国家は「力の体系」であり、「利益の体系」であり、そして「価値の体系」であると言っているわけです。各国の関係は、この体系がそれぞれ複雑に関わり合って動いています。

トランプ大統領と星条旗
私はメジャー・パワーという以上、この三つの体系がしっかりとその国の中に確立していることが大事だと思います。力がゼロの国は、メジャー・パワーたり得ない。利益もそうです。戦後の日本は、この三つの中で主として利益の体系に重点を置いてきたわけですが、それが湾岸戦争で挫折したと思っています。力の体系が足りなかっただけでなく、価値の体系が十分に理解されるものでなかったという面があったのです。その三つの体系をしっかり強靭化していくことが必要だと思っています。今後の日本がメジャー・パワーとして生きていくということは、この三つの体系をしっかりしたものにし、かつ、対外的に説得力を持たなければならないと思います。
ただ、総体としていろいろ批判はされるけれども、説得力を持った体系を今は築きつつあると思っています。国際社会の中でメジャー・プレーヤーとして生きていく能力は十分ある。問題はそうやっていくという覚悟を持っていくことだと思います。
――2023年の『Voice』6月号(宮本雄二・元駐中国大使との対談「歴史的転換点の日本外交 分断と混沌を乗り越える外交力とは」)で、「三つの連立方程式を」とおっしゃっていました。価値観を共有する同盟国・同志国との連携、中国との健全な関係、それとグローバルサウスと親しく付き合う。

国内外の状況を分析する谷内正太郎・初代国家安全保障局長=中澤雄大撮影
谷内 それは今でも基本は変わらないですよね。日本にとっては、これだけ核を持っている国に囲まれている時に、どこかの国の核の傘がないと危ないわけですから、やはり日米同盟は大事だと思います。同時に、私は中国は今世紀最大の国際社会の課題、問題だと思っていますが、その中国がどういう国になっていくにせよ、いかにうまく付き合っていくかは非常に大事です。国際社会全体が米中の対立で動いていくことは間違いないと思うので、日本は両方との関係を最も重視してやっていくということだと思います。
◇憲法九条は誤解のない理解しやすい形に改正を
――集団的自衛権とそれに関連する憲法第九条など、日本の法制度については今後どのように考えますか?
谷内 憲法第九条にしても、集団的自衛権にしても、文理解釈にこだわるのではなく、きちんと現実を踏まえた合目的的な解釈をするべきだと思います。それができないのは、やはり戦前の経験があって、当時の軍部に国民が振り回され、悲惨な目に遭ったということがあって、権力に対する強い警戒感があるわけです。これはある意味では健全な意識ではあるのです。しかし、「国亡びて、憲法残る」であってはなりません。

日本国憲法の原本(国立公文書館デジタルアーカイブより)
憲法第九条については、これまで政府は国際社会の厳しい現実に対応して、特殊日本的な(即ち、外国では理解され難い)解釈論を積み重ねてきました。それは、関係者の間でも全容を把握するのが困難なほど、複雑な論理で組み立てられたガラス細工のようなものになっています。安倍政権下の平和安全法制によって随分改善されましたが、複雑な論理構成であることは間違いありません。防衛の現場ではいろいろ苦労されていることも多いと聞いています。
従って、このような状況をやむを得ないものとして放置するのではなく、第九条の改正を行って誤解のない形で理解し得る条文にする必要がある。第一義的には国政に参画する政治家が責任を持ってそのような作業を行った上で国民に最終判断を仰ぐべきだと考えます。
◇やはり大事な日米同盟
――米国のトランプ政権についてどう見ておられますか?
谷内 トランプ大統領の岩盤支持層は今4割近くいると思います。彼が何を言おうが、何をしようが、ともかく支持する、ということですから、我々もそこを理解する必要があります。私はそれを理解するのに一番良い本はバンス副大統領が書いた『ヒルビリー・エレジー(Hillbilly Elegy)』(光文社刊・2017年)だと思います。低所得ないし所得のない労働者層の環境、あるいは家庭の状況がよく描かれていて、現状に対する不満、エスタブリッシュメントやエリートに対する不満の強さが分かります。
彼らからするとトランプ大統領というのはサクセス・ストーリー、アメリカン・ドリームなんですね。しかし、そういうアメリカがもうチャンスの国ではなくなっているという絶望感がある。そこに生じたポピュリズムですから、我々は本当に気をつけていかないといけない。
一方で、日米同盟はやはり大事ですから、細心の注意を払って十分な対話と協力をしないといけません。それから、トランプ大統領の周辺は一期政権と違ってイエスマンばかりで、大統領に「それはなりません」という人はいない、という所は確かにあります。しかし、ルビオ国務長官、ヘグセス国防長官の最近の発言を見ると、以前のアメリカのメジャーな議論と同じようなトーンで行われているようで、この点は心強く思います。
-300x202.jpg)
トランプ大統領と談笑するバンス副大統領ら(ホワイトハウスHPより)
ただ、問題は国家安全保障会議が形骸化しているように見えることです。マイケル・ウォルツ国家安全保障担当補佐官が(情報漏洩問題で)解任された後、後任がおらず、ルビオ国務長官が代行として兼任しています。副長官もおらず、上級アジア部長はいるけれど、部下がいない。一期政権の時は、しっかりした官僚のスタッフが400人近くいて、私は(国家安全保障担当大統領補佐官の)マクマスターさん、ボルトンさんと頻繁に連絡できていましたが。
◇ソフトパワーを失いつつある米国
――米国の連邦政府が相当痛んでいるのでは。
谷内 アメリカの政府の仕組みは崩されてきていますね。もう一つ、先に亡くなった国際政治学者のジョセフ・ナイさんが言っていた「ソフトパワー」というものが、アメリカにとって非常に強力な武器だったのですが、このソフトパワーが色褪せてきています。米国際開発局(USAID)を廃止する、教育省を廃止する、ハーバード大学への補助金を停止する、留学生を追い出す、不法移民をどんどん国外へ追放する。かつてはアメリカという国は、虐げられた人々、行き場のない人たちの最後の希望の機会を与えてくれる憧れの国だったわけですが、そのイメージはなくなりつつあります。いずれにせよ、アメリカは本当に厳しいと思いますね。
◇分断と対立と混迷の国際社会を生きるには
――米国は、自身が主導してきたリベラルな国際秩序を自ら壊している中で、イスラエルとイランの衝突と停戦、米国のイラン核施設空爆など事態はめまぐるしく変化しています。最後に、改めて日本はこれからの世界を生きるにはどうすれば良いかを伺いたいと思います。
谷内 イスラエルとイランの停戦はいつまで続くのか? イランは核開発を断念するのか? 逆に推進する決意を固めているのではないか? 米国の再介入はないのか? カタール、オマーン、トルコなどの仲介は効を奏するのか? イスラエルに叩かれた過激派勢力はどのような活動を行っていくのか? 中東情勢は混迷を深めており、ウクライナ戦争も収束する見通しは立っていません。台湾周辺や日本周辺の海域でも緊張は高まっています。

エルサレムに張り巡らされた有刺鉄線
イアン・ブレマー氏(国際政治学者)は、トランプ大統領は「地政学上の自傷行為」を行っていると批判しています。同氏は以前より、今日の世界はグローバル・ガバナンスに責任を持つ政府の存在しない「Gゼロ」の世界と言っています。多極化、無極化の世界とも言われます。世界は真に「分断と対立と混迷」の真っ只中にあり、私達は深刻な不安と懸念を持って生きています。
とはいえ、私達は立ちすくんでいるわけにはいきません。わが国としては、世界の中のメジャー・パワーとして生き抜く覚悟を持って、そのためのわが国独自の座標軸をしっかりと固めて進んでゆく必要があります。外交は国際舞台で国益を追求する場です。したがって、国益とは何かを改めて確認する必要があります。
まず、日本国民の生命と財産を守ることが第一義的に重要です。そして、日本の主権、領域、歴史、伝統、文化を守ることです。更に、国際社会共通の自由、人権、民主主義、法の支配のような価値観を守ることです。

イランの首都テヘラン
次に、基本的な外交政策としては、第一に日米同盟を維持、強化することです。第二に、対米一本足打法に偏ることなく、志を同じくするEU諸国やインド、豪州、ニュージーランド、韓国、ASEAN諸国との連携を強化することです。第三に、地球環境の保護や感染症対策のような国際公益のために協力、貢献することです。
「ピンチはチャンス」と言いますが、日本外交が世界の中で一定のリーダーシップを発揮する機会の窓は、このような時代にこそ開けるのではないかと思います。(取材・構成=冠木雅夫)

谷内 正太郎(やち・しょうたろう)
1944年石川県金沢市生まれ、富山県育ち。東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。69年外務省入省、米タフツ大学フレッチャースクール研修、ハーバード大学国際問題研究所フェロー。人事課長、ロサンゼルス総領事、条約局長、総合政策局長などを歴任。内閣官房副長官補として安倍晋三官房副長官の下で拉致問題などに取り組む。2005年1月~08年1月まで外務事務次官。退任後、09年に政府代表、12年第二次安倍政権での内閣官房参与などを経て、14年1月に初代の国家安全保障局長(19年9月まで)に就任し、第二次安倍政権の外交安全保障政策を支えた。20年より富士通フューチャースタディーズ・センター理事長。著書に『外交の戦略と志』(産経新聞出版)。
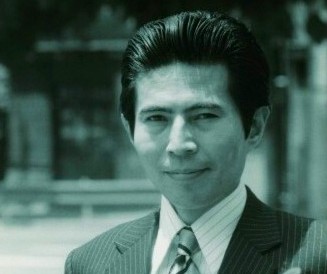



-500x500.jpg)


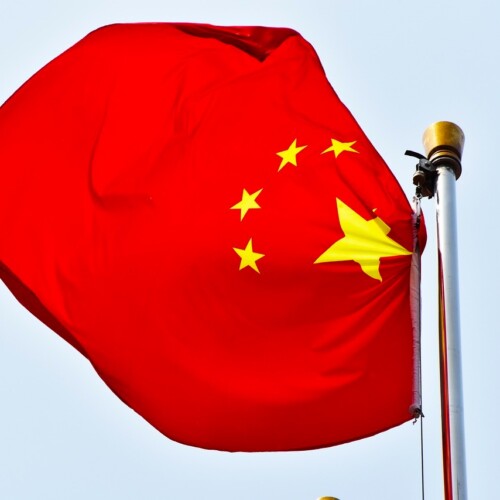

のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより)-500x500.jpg)
