一水四見 多角的に世界を見る
小倉孝保

4月21日、88歳で亡くなったフランシスコ・ローマ教皇
第11回 ブーツを脱いだローマ教皇
英語の慣用句に「Die with your boots on(ダイ・ウイズ・ユア・ブーツ・オン)」がある。直訳すると、「ブーツを履いたまま死ぬ」となる。かつて「絞首刑に処される」を意味したこの言葉は、最近では「最後まで働き続ける」の意で使われる。
先月亡くなったバチカンのフランシスコ・ローマ教皇についても、この表現が用いられた。外遊に同行した外相、ポール・ギャラガー大司教が英BBCとのインタビューで「教皇はブーツを履いたまま死ぬことを望みました」と述べている。休暇を取ったのは「67、8年前だと思う」と言うのだから、労働者なら完全に「働き方改革」に逆行している。
大司教の印象に残っているのは2015年の中央アフリカ訪問だ。アフリカのほぼ中央にあるこの国では13年、宗教対立による内戦が起き、首都バンギのイスラム教徒の多くが地方に避難した。教皇が訪問に意欲を示すと、周りは「危険過ぎる」と翻意を促した。その時、教皇はこう言った。「もし誰も来ないならいいですよ。一人でも行くから」
キリスト教武装民兵に包囲されたバンギのモスクに到着した教皇は、イスラムの教えに従い靴を脱いだ。聖地メッカに向かって一礼した後、数百人の男性に呼び掛けた。
「キリスト、イスラム両教徒はきょうだいです。憎悪、復讐、そして宗教間の暴力にノーと言わなければなりません。神は平和です」。スピーチの最後は、「平和」を意味するアラビア語「サラーム」で締めくくられた。

サンピエトロ大聖堂
教皇が在位中に訪ねた国は60を超える。イタリア・ランペドゥーサ島では13年、難民船事故の犠牲者を追悼し、19年の広島訪問では被爆者を抱擁した。
イタリア系移民の子として1936年、アルゼンチンに生まれた。名前はホルヘ・マリオ・ベルゴリオである。2013年の教皇即位の際、フランシスコを名乗った。過去の教皇にはない名前である。
「アッシジのフランチェスコ」(1182~1226年)は貧しく、謙虚な人々を保護したとされ、教皇はこの聖人から名をとったと考えられている。
パレスチナ人に対して同情的で、昨年のクリスマスと今年の新年には、イスラエルによるパレスチナ自治区ガザ地区への攻撃を批判した。
ギャラガー師によると、教皇には、外国の指導者や政治家との公式行事では眠そうにしたりたり、見るからに楽しんでいないような表情を浮かべたりする、人間らしい面もあった。偉人との面会よりも、市井の人々、特に若者に囲まれることを好んだという。
カトリック教会については、聖職者による児童などへの性的虐待が2002年に明らかになった。欧州などではカトリック信者の減少を加速させたともいわれている。
しかし、国際協調よりも「自国第一主義」が拡大する今、軍事や経済とは縁の薄い国が存在し、そのトップが「強者の論理」とは別の考えを示すことの意味は小さくない。
亡くなる2週間前、教皇はこう言ったという。「ユーモアのセンスをなくさないよう」。ようやくブーツを脱いだ教皇は遺言に従い、庶民的な地区の大聖堂に埋葬された。
5月7日からの教皇選挙(コンクラーベ)で、米国出身のロバート・プレボスト枢機卿(69)が第267代教皇に選ばれ、教皇名をレオ14世とした。米国出身の教皇は史上初めてである。長年南米ペルーで活動し、貧しい人々や移民に寄り添ってきたと言われている。
新教皇はサンピエトロ大聖堂のバルコニーから、「平和が皆さんと共にありますように」と呼び掛けた。

小倉 孝保(おぐら・たかやす) 毎日新聞論説委員
1964年生まれ。毎日新聞カイロ、ニューヨーク、ロンドン特派員、外信部長などを経て現職。小学館ノンフィクション大賞などの受賞歴がある。新著に『プーチンに勝った主婦 マリーナ・リトビネンコの闘いの記録』(集英社)。

-800x550.jpg)
のグラビア(国立公文書館デジタルアーカイブより).jpg)
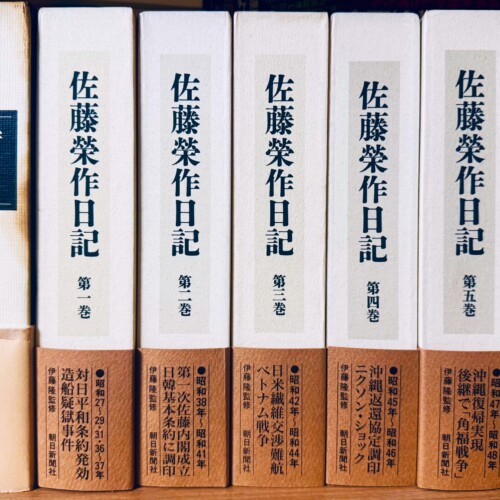

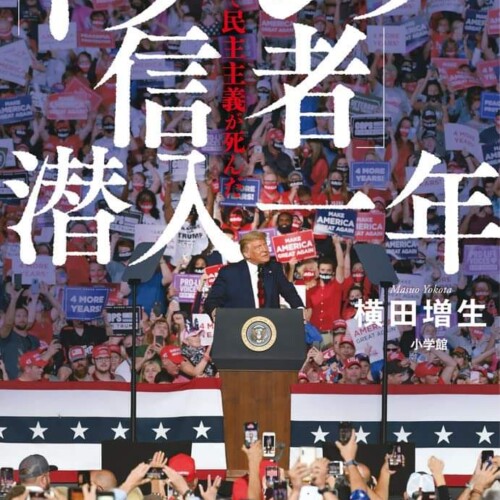
-500x457.jpg)



