外交裏舞台の人びと
鈴木 美勝(ジャーナリスト)

石油輸入問題を協議するため来日し、佐藤栄作前首相を表敬したキッシンジャー国務長官(当時)=1973年2月撮影(『キッシンジャー秘録❷ 激動のインドシナ』より)
第14回 1969年沖縄返還問題──
日米交渉<表>と<裏>の構図⑥
キッシンジャーとは何者なのか
◇大統領補佐官との面会約束で浮かんだ疑問
1969年7月17日、若泉敬とのやり取りの最後に、モートン・ハルペリン(国家安全保障会議〔NSC〕事務局計画担当官)は「明日は、自分も同席するつもりだ」と言って、ホテルを辞した。ところが、翌18日午前11時、ハルペリンからの電話で、思いがけぬことを告げられる──「ヘンリー(・キッシンジャー国家安全保障担当大統領補佐官)に同席を断られた」。「なぜだ」と若泉。彼はぶっきらぼうに答えた──「分からん」。
ハルペリンはジョンソン政権の国防次官補代理として沖縄問題に関与して以来、ニクソン政権になっても引き続き、キッシンジャーの下で国家安全保障会議のスタッフとして同問題に取り組んできた。沖縄問題に最も詳しい知日派の一人と誰もが認めていた。何故に同席を拒否されたのか。疑問が消えぬままに、キッシンジャーとの約束の時間が近づいてきた。若泉はホテルを出た。
◇同席者なしの秘密会談
この日午後4時40分、サングラスをかけた一人の日本人が通用門を潜って、ホワイトハウスの地下1階に降りた。ニクソン大統領と家族の写真で埋め尽くされた廊下を通って案内されたのは、ジョンソン政権時代に大統領特別補佐官ウォルト・ロストウと交渉した時と同じ、懐かしいオフィスだった。

『キッシンジャー 理想主義者2』
そこには、頑丈そうな鼻に眼鏡をかけ、唇の厚ぼったい小柄な男が待っていた。洞窟でしゃべる時〔註1〕のような、低く落ち着き払った響く声で、聞く者を魅了するキッシンジャーだった。
若泉が首相・佐藤からの信任状を出すと、男は頷き、訊いてきた。「一人同席させてもいいか」──何のために? 「記録を取るためだが、絶対信頼できる人物だ」──このひと言で若泉は、ハルペリンの電話以来、頭を占めていた疑問が解けて行くのを感じた。
後々、分かったことだが、ハルペリンはマスコミへの秘密漏洩の嫌疑(「核抜き」決定をめぐって一部報じられた同年6月3日付『ニューヨーク・タイムズ』紙の報道か)がかけられ、自宅にFBI(連邦捜査局)の電話盗聴装置が仕掛けられていた。若泉が東京からかけた国際電話も盗聴され、FBIの大統領宛秘密報告にも載っていたと言われる。現に大統領ニクソンの盗聴指示に同意して、容疑者リストを提出したのは、誰あろうハルペリンの上司、このキッシンジャーだった。〔註2〕
◇秘密主義と政治的ホットライン開設
「徹底した秘密主義者」──若泉は、キッシンジャーの代名詞となる世評の一端を垣間見た思いがした。
「記録をとる必要はない。お互いに記憶しておけばよい。どうしても必要なら、(私が)あとでメモにする」〔註3〕。若泉はこう申し出て、キッシンジャーが求めた同席者を拒否した。
こんな形で始まった若泉─キッシンジャーの日米裏舞台外交だが、21日の再会談を含めた2度の秘密接触により、若泉は今回訪米の最重要ミッション──即ち、今秋に予定される佐藤─ニクソン首脳会談を成功裏に終わらせるため、ホワイトハウス-首相官邸間の政治的ホットラインを開設するよう提案・合意を取り付ける──という所期の目的を達成することになる。
若泉はこの時、沖縄返還問題をめぐる佐藤の基本的な立場・見解、ニクソンへの質問を、キッシンジャーに詳細に伝えている。
1、ニクソン大統領は核兵器を沖縄から撤去することに同意するであろう、との未確認報道がある。この肝要な質問に、率直かつ正直な回答をして頂けないか。
2、佐藤首相は、沖縄返還後の米軍基地の“緊急事態の自由使用”の問題についてのニクソン大統領の考え方を知りたいと望んでいる(原文のまま)。この問題についての首相の立場は、柔軟かつ現実的である。今後日米双方の外交官による折衝の主たる任務は、緊急事態における作戦行動の自由に関するフォーミュラを慎重に作り出すことであろう。〝事前協議〟は、真の緊急非常事態の場合、「ノー」よりも「イエス」を意味するものでありうるし、また事実意味するであろう。これらのかなり複雑な諸問題は、今後何カ月かの外交交渉において討議され、かつ明確に定義されなければならない。
遺憾ながら、佐藤首相は現在の日本国内における政治情勢に鑑み、米国が、沖縄返還後、緊急事態において基地を自由に使用することが可能であるということを公然と認めることはできない。そこで、大統領と首相との秘密了解事項としておくべきか、何か別の方法を獲るべきかという極めて重要な問題が出て来る。もしそれが秘密の了解事項であるとしても、それは両国政府首脳の後継者を拘束するものになるであろう。
◇国務省外し──「知っているのは4人だけ」
21日の若泉─キッシンジャー会談は、夕方に大統領の記者会見もあって夜8時半からようやく始まった。席上、キッシンジャーは若泉に、改めてニクソン大統領がホットライン開設に賛成であると伝えた。そして、大統領と協議した結果、国務長官には知らせないことにしたので、「日本側も同様にしてもらえるか」と要求した。若泉は同意した。これで、この秘密チャネルを知るのは、佐藤─ニクソンと若泉─キッシンジャーに限定されることになった。
キッシンジャーは若泉に強く念押しした。「(知っているのは)4人だけだね(Just four of us!)」〔註4〕。2人は主に電話連絡を配慮して“暗号表”を作成、若泉はキッシンジャーを「ドクター・ジョーンズ」と呼び、若泉の符牒は「ミスター・ヨシダ」にした。
米側はウィリアム・ロジャーズ(国務長官)、日本側は愛知揆一(外相)、保利茂(官房長官)、木村俊夫(官房副長官)を外して「政治的ホットライン」が設定された。4人以外には不可視の枠組みで、秘密の日米チャネルがつくられたのである。

米国務省のHPより(https://www.state.gov/)。「私たちの使命は米国の安全、繁栄、民主主義の価値を守り、促進し、すべての米国人が繁栄できる国際環境を形成すること」と掲げている
「機会をとらえて国務省の縄張りに踏み込むことを楽しみにしていた」キッシンジャー〔註5〕の見事な国務省外しだった。その上で、「問題は」と、キッシンジャーは言葉の調子を変えた。「緊急時の基地の自由使用のことだが、……事前協議条項について日本側からどんな自由使用の保証を与えてもらえるだろうか。……原則的な合意ができれば、核を沖縄に貯蔵ないし配備することをやめることを考慮してもいい」、さらに「かりに一旦撤去したとしても、……緊急事態が発生した場合、……核を再び持ち込む必要が生じるかもしれない。その権利をわれわれは保持しなければならない。日本政府はどのようにしてその点を保証してくれるのか」。若泉は、即答を避けた。持ち帰って、佐藤に「よく説明し、返事をもらってくる」と答えた。〔註6〕
その徹底した「秘密主義」と併せてキッシンジャーの月旦に付きまとうものに、「国務省嫌い」という評があるが、その一点が鮮明になったキッシンジャーの要求だった。
これに絡んで興味深いキッシンジャーの発言記録がある。インタビュアーは、「キッシンジャーが恋に落ちた」と言われるフランス人ジャーナリスト、ダニエル・ユヌベル。彼女の研ぎ澄まされた感覚で、インタビューを基に人間キッシンジャーを解剖して見せた本である。数多あるキッシンジャーをテーマにした書籍のうち、今でも異彩を放つ鋭い分析に、若泉自身も興味深く読み、称賛した一書だった。
◇「恋人」ユヌベル女史の分析
1969年11月、ユヌベル女史は、4カ月前に若泉が極秘に訪れたのと同じ地階のオフィスで、謎多きキッシンジャーと初めて会見した。
キッシンジャーは、1923年ワイマール共和政時代のドイツ・バイエルン州に生まれ、38年ナチス政権のユダヤ人迫害から逃れて米国へ亡命、帰化して四半世紀の一介の大学教授。あらゆる点で不利な立場にあり、ハンディキャップを負っていた。美男子でも、優雅でも、スポーティーでも、上品でもない。気が小さくて、ドイツ訛りの英語を話し、半ば無名の境遇から引き上げられ、頂上に押し上げられた。そんな男が、ここ超大国の安全保障の最前線に、知能だけを持って丸裸でホワイトハウス入りしたのだ。〔註7〕
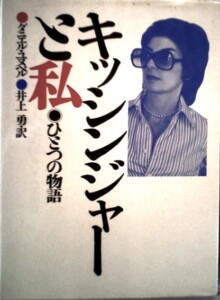
ユヌベル著『キッシンジャーと私』
ユヌベルは、当時のキッシンジャーについて分析した。自己イメージをどう大衆に投影するか──謎めいた現在の世評をそっくりそのままに、幸運にも手に入れたアメリカン・ドリームに酔いしれて目を回すこともない。その一方で国家的重責に屈服することもなく、また、手に負えぬ自身の偏執性と、世間で持て囃はやされたい渇望の双方を同時に満足させようと懸命になっていた──と。キッシンジャーがちょうど、権力を強く意識し始めた頃のことだった。
◇ニクソンが抜擢したわけ
それにしても、大統領ニクソンが、亡命ユダヤ人キッシンジャーを外交安全保障問題の個人的助言者で安全保障会議のトップに据えたのはなぜか。
ユヌベルは、今さらのように考え直して、結論づけた。アポロ11号の人類初の月面着陸(1969年7月)によって全米が湧き、栄光の絶頂にある超大国の安全保障と世界での役割のカギを、学術界以外では知名度や財産もない上に、ユダヤ人である一市民に預けた。それは「偏見から解放された讃うべき意志も忘れてはならないが、アメリカ憲法の自由主義と同時に」亡命者で帰化したこの人物の「個人的価値にたいしてささげられた敬意だ」と。〔註8〕
同じ欧州生まれ、個人主義、人間的な熱意──キッシンジャーとユヌベル、二人の間には「割らねばならぬ、いささかの氷もなかった」。何の衒いもなく、二人はざっくばらんに話し合った。
いわく「女というものは、自分が支配できると思い込んだ男性にいっそう関心を持つ。とくに、その男性が聡明な場合は」──〔註9〕。ユヌベルはインタビュー記事の結末をつけるため、取材した同じ週の金曜日に再びワシントン行きシャトルに飛び乗った。
◇反官僚主義
2度目の会見で、ユヌベルは意表を突くような質問をした。ハーバード大学教授からホワイトハウス入りして1年の間で「いちばん意外だったことをふたつ挙げてほしい」と──。
キッシンジャーは「ひとつは国務省官僚の利己主義だ」と言い放って続けた。「彼らが関心を持っているのは、結果ではなくて仕事をすることなのだ。わたしは……そんなことではないかと疑っていた。しかし、合衆国と世界とが当面するいろんな問題がはかり知れないほど巨大なことを考えると、個人的権力のことしか考えないというのは気違い沙汰ではないかね。偽善のほうがまだましだろう」と。
そして「2番目は」と言えば、「あることが起ころうとしているのを知っていながら、それを回避するために、なにひとつできないことだ。たとえば、チェコスロバキアへのロシアの介入だ。わたしはそれを予見していた。わたしはなかなかりっぱなパイサニス(デルファイ宮殿の巫女)なんだ。しかし、行動する余裕はまったくなかった。」
どちらの発言も、その批判の矢がプロ意識に欠けた職業外交官や蔓延る負の官僚主義に向けられていた。キッシンジャーは重ねて「役人の冒険精神の欠如」「なにごとも達成できない無能力さ」を力説した。そして、封鎖された官僚の問題を「われわれの時代のもっとも恐るべきもののひとつだ」と、ユヌベルに説いた。〔註10〕
-300x228.jpg)
慰霊のため硫黄島を訪れた若泉敬=1996年1月撮影(麗澤大学モラロジー研究所所蔵)
◇キッシンジャーの政官学論
連載13回冒頭、「政治なる者は術(アート)であり、学(サイエンス)にあらず」という、明治期の外交官かつ政治家の陸奥宗光の言葉を引いた。時代が大きく変わり、国柄・国の規模も異なるアメリカで、学者出身の外交家キッシンジャーは、陸奥とは異なる視点から政官学の在り方を提示した。
「行動人の危険性は、戦略的目標を忘れて、戦術に熱中する点にある」とした上で、キッシンジャーが評価したのは、物事の本質をつかむ術を知り、予感に従って行動する勇気を持つネルソン・ロックフェラー〔註11〕の芸術的直観、ロバート・ケネディ〔註12〕の強い信念と大きな同情心、そして、ド・ゴール〔註13〕のように、現在を操ろうとせず、もっと遠くを見て未来を整備することを心がける人間だった。〔註14〕
裏舞台外交が動き出した7月17日の極秘接触が終わった後、キッシンジャーは、若泉に向けて独特の魅力ある笑顔を見せた。「君とは、これから何度でも会おう。お互い旧知の学者仲間だが、これからはそれ以上に友人として協力し合おう。お互いファースト・ネームで呼ぼうや」〔註15〕。若泉は安堵して、ホワイトハウスを出た。
ユヌベルより4カ月前に会った密使・若泉は当時のキッシンジャーの印象について「その表情は巨大な権力をエンジョイし始めている男の心理を映し出している」〔註12〕と描出した。
明らかに、官僚には見せない学者キッシンジャーの顔だったが、若泉の交渉相手となったこの男は、鋭い戦略眼と巧みな交渉術を備えつつも、米国内政の知見に乏しいという短所を併せ持つ人物であった。やがて、それは日米繊維問題という形で、キッシンジャーと若泉双方に交渉力の真価を問いかけてくるのである。
<註>
〔1〕〔7〕〔8〕〔9〕〔10〕〔14〕ダニエル・ユヌベル『キッシンジャーと私 ●ひとつの物語』
〔2〕〔3〕〔4〕〔6〕〔12〕〔15〕若泉敬『他策ナカリシヲ信ゼムト欲ス』
〔5〕『ジョンソン米大使の日本回想──二・二六事件から沖縄返還・ニクソンショックまで』
〔11〕ニューヨーク州知事やフォード政権の副大統領を務めた
〔12〕ジョン・F・ケネディ大統領の実弟で、司法長官を務めた。後に大統領候補指名選挙キャンペーン中に暗殺された
〔13〕第二次大戦後のフランスで臨時政府首相、第五共和制下で初代大統領
<他の参考文献>
陸奥宗光『蹇蹇録』、『佐藤榮作日記』第3巻、『キッシンジャー秘録』第2巻、宮川徹志『僕は沖縄を取り戻したい──異色の外交官・千葉一夫』、「NHKスペシャル」取材班『沖縄返還の代償 核と基地 密使・若泉敬の苦悩』
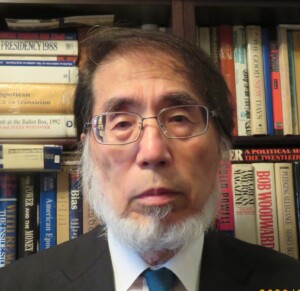
鈴木 美勝(すずき・よしかつ)
ジャーナリスト(日本国際フォーラム上席研究員、富士通FSC客員研究員、時事総合研究所客員研究員)、 早稲田大学政経学部卒。時事通信社で政治部記者、ワシントン特派員、政治部次長、 ニューヨーク総局長を歴任。専門誌『外交』編集長兼解説委員、立教大学兼任講師、外務省研修所研究指導教官、国際協力銀行(JBIC)経営諮問・評価員 などを経て現職。著書に『日本の戦略外交』『北方領土交渉史』(いずれも筑摩書房)、『いまだに続く「敗戦国外交」──「衆愚」の時代の新外政論』(草思社)、『小沢一郎はなぜTVで殴られたか──「視える政治」と「視えない政治」』(文藝春秋)、『政治コミュニケーション概論』(共著、ミネルヴァ書房)。


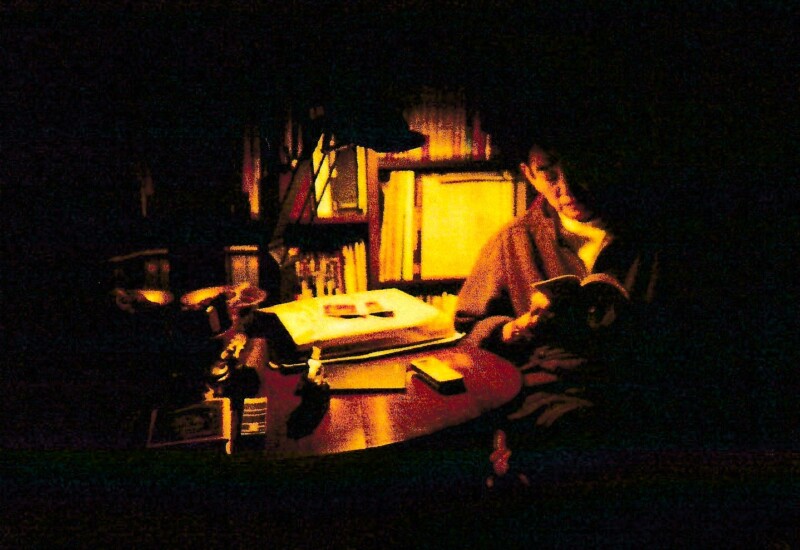

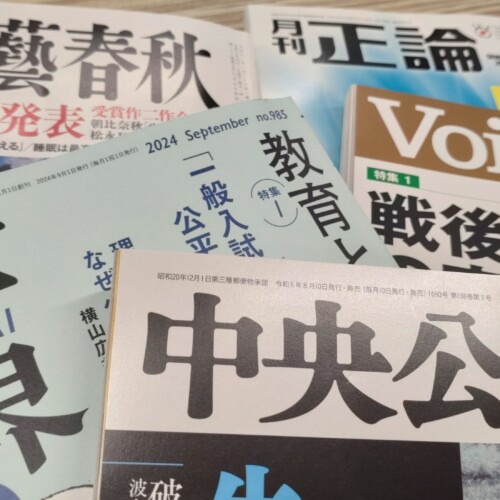

-500x500.jpg)



